6.単独性と「住み込み」のフィールドワーク
河川敷を超えてつくられた「コモン=共」を基盤とする鈴木さんの0円生活は、「ホームレス」に一般化できない、鈴木さんだからこその自のやり方だと言ったほうがいいかもしれません(ただし、そのようなやり方は芦屋の例にも見られるはずですが)。しかし、人類学的な民族誌に通じることですが、坂口さんの本は、むしろ一般化することをせずに、鈴木さんを「唯一無二」の存在として付き合い、そこからそのような生活を描きだすことで、私たち一人ひとりの生き方にも通じる「普遍性」がそこにあることをみせてくれています。坂口さんは、本の「おわりに」で、つぎのように書いています。
隅田川に家を建てるという行為は許されているものではない。しかし鈴木さんの家を調べれば調べるほど、なぜこの生活が許されず、周りには巨大な建造物が建っていくのか、正直分からなくなっていった。なんだろう、この矛盾は。どうにかならんものか。新しい視点はありえないのか。
僕としての提案は、ホームレスという枠から鈴木さんの生活に焦点を当てるのではなく、唯一無二の1人の人間の生活として捉えてみるということだ。この本に書いてきた鈴木さんの生活には多様性が溢れている。それは僕たち1人1人にも当てはまるはずだ。全体だけで把握せず細部も常に自分の目で見て確認しないと事実は分からない。[坂口 2011:288]
6-1.唯一無二の単独性から通じる普遍性
ここで書かれていることは大事なことです。「ホームレスという枠」から捉えて書いてしまうと、鈴木さんの生活や考え方・やり方は、最初から自分たちとは異なる枠のなかの話になってしまいます。また、この坂口さんの本に対しては、ホームレスの全体像を描いていない、障害者や親族関係の欠如といったことから望まずにホームレスになってしまう「ホームレス問題」を扱っていないという批判がありうるでしょう。しかし、そのような批判はそれぞれ「唯一無二の1人の人間の生活」を「ホームレス」という枠によって捉えることにほかなりません。文化人類学(民族誌)による「異文化」の記述が意義のあるものになるのは、異文化でありながら、私たち一人ひとりの生き方に通じる「普遍性」があるからでしょう。そして、その普遍性は、それぞれ唯一無二の人たちの単独性を描くことによって生じてくるのです。そして、それは、人類学固有の方法である「フィールドワーク」からくる独自の視点とも関連しています。
6-2.「住み込み」のフィールドワークと「真正性の水準」
第1回の「人類学の生い立ち」のところで、人類学のフィールドワークと他の学問のフィールドワークの違いについて話しました。人類学者のフィールドワークは「住み込み」のフィールドワークであり、社会学者など他の人文・社会科学のフィールドワークは「通い」のフィールドワークだという違いです。野宿者(ホームレス)のフィールドワークについていえば、社会学者は、彼らを支援したりしながら、彼らのところに通ってインタヴューをするという調査をするのですが、人類学者は、自らもホームレスになって住み込むという違いがありました。そこにあるのは、ひとことで言えば、「生活」があるかないかという違いです。そして、この「住み込み」のフィールドワークが人類学独特の視点を生んだのだと言いました。
では、人類学独自の視点とは何なのでしょう。レヴィ=ストロースは人類学独自の視点として、「真正性の水準」という社会の様態の区別を挙げています。「真正性の水準」(ほんもの性による区別)とは、5000人の社会と500人の社会との区別です。レヴィ=ストロースは、1986年の日本での講演を集めた『レヴィ=ストロース講義』のなかで、この「真正性の水準」について、つぎのように言っています。
住民のほとんど全員が顔見知りであるような村や、大都市のなかの一郭であれば、人類学者の扱い慣れた調査地ともなります。彼は人口5百の村では困難を感じません。それなのに、大都市、いや中都市でさえ、人類学者は調査に手こずるのです。なぜでしょうか。
5千の人びとが作る社会は、5百の人びとが作る社会と同じではないからです。5千人の社会では、コミュニケーションは個人を中心に、「個人間コミュニケーション」モデルにそって作られてはいません。(コミュニケーション理論の用語を使えば)「発信者」と「受信者」の存在の現実感は、複雑な「コード」と「中継」の背後にかくされてしまうのです。
人類学の社会科学への最大の貢献が、二つの社会生活の様式を決定的に区別した点にあるということは、おそらく将来、いっそう明らかになるでしょう。
二つの社会生活の様式とは、ひとつは当初、伝統的で古代的なものと見なされた「真正性」の社会の生活です。そしてもうひとつは、より新しく出現した生活の形態です。後者には前者のタイプの様式がまったく欠けているわけではありません。むしろ「まがいもの」らしさのしるしを帯びた、より広大な全体のなかに、部分的で不充分であれ「真正性」をそなえた集団が島のように点在する、そうした形態なのです。[レヴィ=ストロース 2005:44-45]
6-3.「真正な社会」と単独性どうしのつながり
この区別は、他の人びととの対面的なコミュニケーションによる小規模な「真正な社会」と、近代社会を典型とする、より後になって出現した、文字や法や貨幣といったメディアに媒介された間接的なコミュニケーションによる大規模な「非真正な社会」の区別ですが、レヴィ=ストロースは、「まがいもの(非真正なもの)」だからいけないとか、そのようなものをなくすべきと言っているわけではありません。その二つの体験は異なったものであり、関係もまた大きく異なっているのであり、それを混同してはいけないということ、そして、人類の文化は、ことばも文化も社会組織もほとんどの間、「真正な社会」において作られてきた(それが「真正な」という意味である)と言っているのです。
そして、そのような「真正な社会」は、近代社会や都市でも失われたわけではないとレヴィ=ストロースは、「『まがいもの』らしさのしるしを帯びた、より広大な全体のなかに、部分的で不充分であれ『真正性』をそなえた集団が島のように点在する」のだと述べて、「近代的社会の研究にしだいにつよく関心をもつことによって、人類学は、近代社会に『真正の面』を認知し、それをとり出そうと努めてきた」のだと言っています。
レヴィ=ストロースは、真正な社会にはあった「人びとが互いにまるごと経験し、具体的に知り合う」[レヴィ=ストロース 2005:41]ということは、非真正な社会では不可能になると言います。つまり、真正な社会では、さまざまな側面をもつ個々の人間が「まるごと」捉えられるのに対して、非真正な社会では、人と人との関係は、法や書類や貨幣といった一般化されたメディア(媒体)を介した間接的な関係になります。逆からいえば、真正な社会では、一人ひとりの人柄や行動はけっして、階級や職業や世代といった比較可能で代替可能な属性や属性の束に還元されないがゆえに、「単独性」(交換不可能なかけがえのなさ)をもっているのに対して、非真正な社会においては、人は民族・階級・ジェンダーといった、明確に分割され一般化された属性(カテゴリー)に還元された、比較可能な存在としてのみ捉えられるのです。
この「真正性の水準」という「世界のある種のとらえ方、あるいは、問題を提起する独特のやり方」から、人類学独特の感覚が派生してきます。すなわち、真正な社会では一人ひとりの人間が単独性において捉えられ、そのアクチュアリティが認識されるのに対して、非真正な社会においては、明確に分割され一般化された属性(カテゴリー)において、単独性を捨象したリアリティにおいて認識されるという違いがあるという感覚、そしてそこから社会というものを考えるという視点こそ、人類学独特の視点なのです。
坂口さんが、「僕としての提案は、ホームレスという枠から鈴木さんの生活に焦点を当てるのではなく、唯一無二の1人の人間の生活として捉えてみるということだ」と言っていることは、単独性どうしのつながり、社会の「真正な面」をとらえて描こうとする人類学的な視点と重なっているのです。
次回からは、ミヒャエル・エンデの名作『モモ』を読んで、単独性どうしのつながりからなる「真正な社会」とは具体的にどのような社会なのかを考えてみましょう。
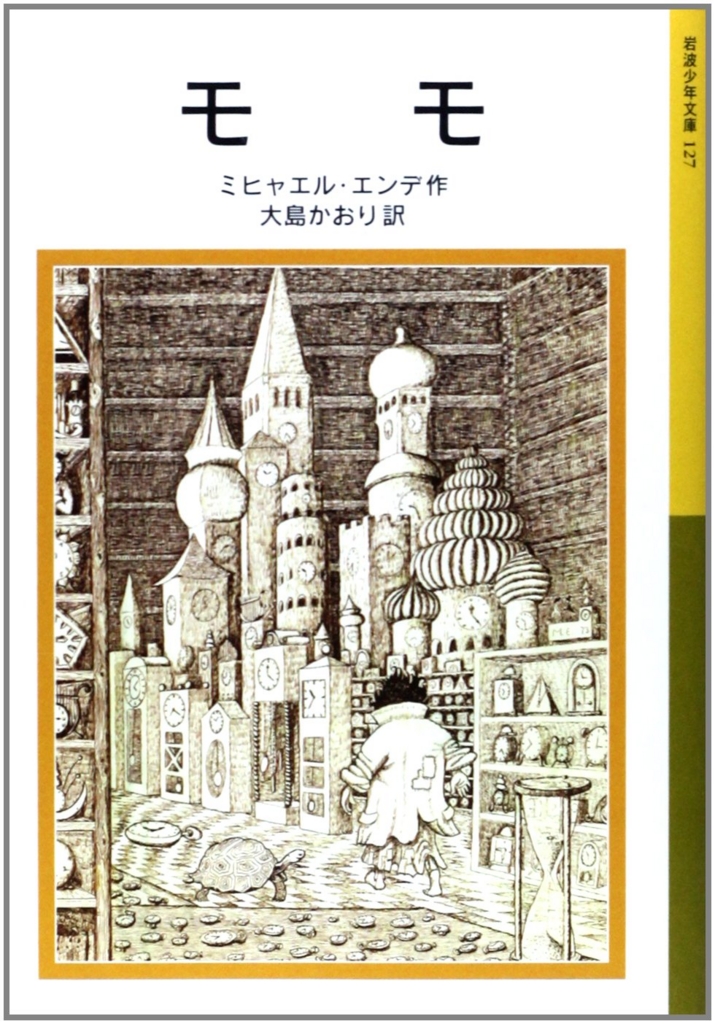
【参考文献】
坂口恭平
2011 『TOKYO0円ハウス0円生活』河出文庫(初版2008年大和書房)
レヴィ=ストロース、C
2005 『レヴィ=ストロース講義――現代世界と人類学』川田順造・渡辺公三訳、平凡
社ライブラリー